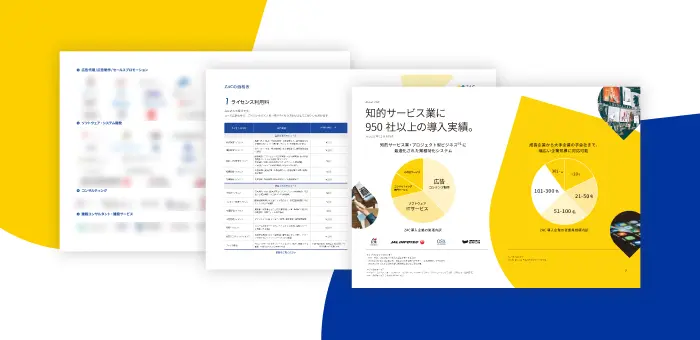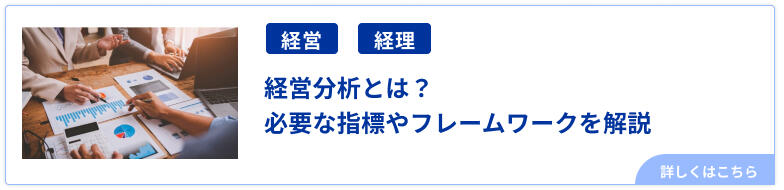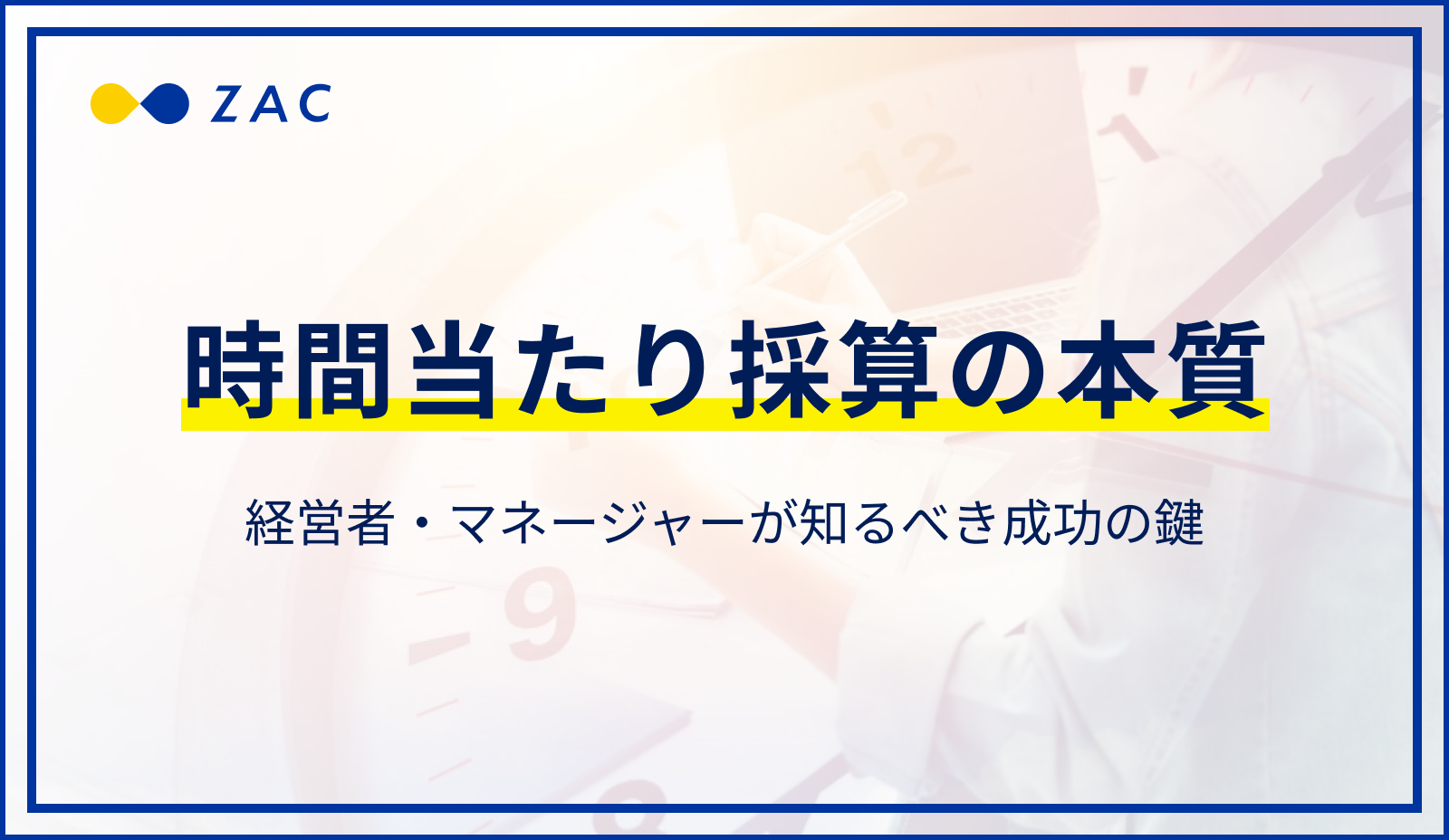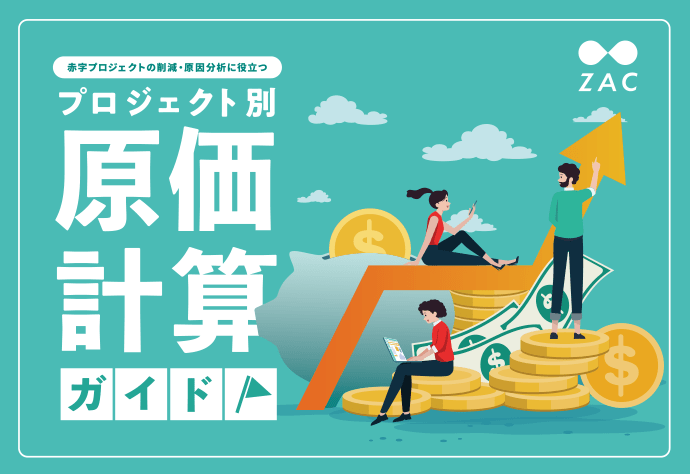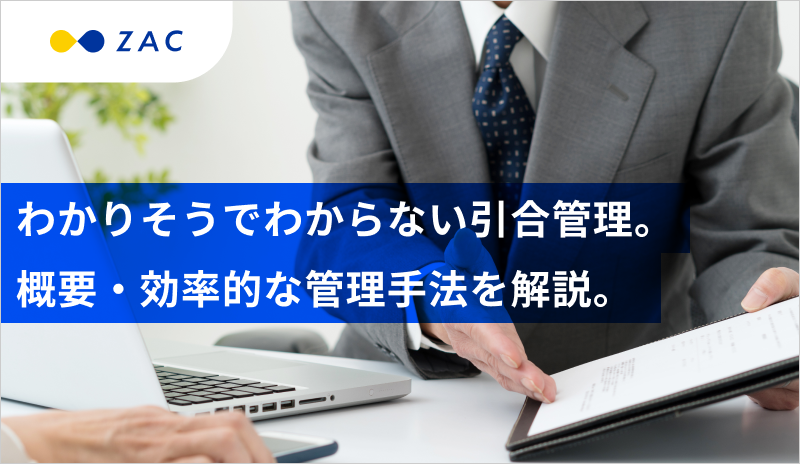経営指標の具体例。タイムリーな経営判断に必要なこと

2025/1/31公開
企業の成長に欠かせないのが、経営指標を用いた経営分析です。タイムリーな経営分析を行うためには、経営指標を理解したうえで正しく活用することが大切です。そこで本記事では、経営指標の具体例とともに、タイムリーな経営判断を行うために実施すべきことを紹介します。
効率的に利益を生み出し、企業を成長させたいと考える経営者の方や、経営指標をもとに分析を行いたい経理・財務担当者の方はぜひ参考にしてください。
目次
経営指標とは
経営指標とは一般的に、企業の決算書である財務諸表(財務三表)を用いて算出する、会社の経営状態を表す数値のことです。財務三表とは、以下の3つが記載された書類を指します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
これらの書類には、売上高や利益、原価、資本、キャッシュフローなどが記載されています。その数値を組み合わせて企業の成長性や財務状況の健全性、業績などを算出し、経営状況の指標とするのです。
経済指標との違い
経営指標と似た言葉に「経済指標」があります。経済指標は、国家や地域の経済状況を表す数値のことです。具体的には、GDP(国内総生産)やCPI(消費者物価指数)などを指します。政府や民間団体による調査結果をもとに、その国・地域の景気動向や平均時給、インフレ率、失業率など経済全体の状況に関する数値を算出したものです。
一方の経営指標は、個々の企業の経営状態を表す数値となっており、その点が経済指標と異なります。
KPIとの違い
KPIとは、Key Performance Indicatorの略で、「重要業績評価指標」のことです。企業や組織が立てた目標を達成するため、必要なプロセスごとに設定する数値指標を指します。 KPIを設定することで、最終目標に向けた進捗を具体的に想定し、管理しやすくなります。企業全体の状態やパフォーマンスを測定する経営指標と異なり、特定の目標を達成するための進捗や達成度合を図るための指標がKPIです。
経営指標が重要視される理由
決算書をベースに算出される経営指標は、企業の経営状況を把握するために重要な数値です。企業において経営指標が重要視される理由は、主に以下の3つが挙げられます。
自社の経営状況を客観的に可視化できる
経営指標は、決算書などの客観的な数字から算出されるため、個人の主観抜きに自社の経営状況を可視化できます。個人の主観が入ると、状況の把握や対策立案が偏りがちです。そこで経営指標を用いることにより、冷静かつ客観的な状況把握が可能となるのです。
他社との比較ができる
決算書はどの企業も同様の計算方法で数値を出しているため、その決算書に基づいた経営指標は、同じ軸での比較が可能です。異なる事業を行なっている企業同士でも同じ基準で比較できるため、他社との比較による自社の弱みや強化すべきポイントを明確にできます。
経営の方針・見直しに役立つ
経営指標によって、企業の成長性や収益性、生産性などの現状を正確に把握でき、経営方針の策定や見直しに役立ちます。また、一つの指標を追い続けることで、長期的な施策の効果を測れるものです。
経営指標の具体例。基本となる5つの分析軸
経営指標として、複数の数値が挙げられます。その指標をもとに、さまざまな切り口で企業の経営状況を分析することが可能です。ここでは、一般的かつ基本となる5つの分析軸を紹介します。経営指標を活用したいと考えている方は、まずはこの5つの軸で分析を行ってみてください。
収益性
収益性とは、企業が本業でどれだけの利益を上げているかを表すものです。また、資本をもとにどれだけ効率よく利益を生み出せているかを表します。収益性が高いということは、同じ資本からより大きな利益を生み出す力があることを示します。一方、収益性が低ければ、かけた費用の割に利益が得られていないことを示します。
収益性につながる経営指標は以下のようなものがあります。
- 総資産利益率(ROA)=当期純利益÷総資本×100
- 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益÷自己資本×100
- 売上高総利益率=売上総利益÷売上高×100
- 売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
- 売上高経常利益率=経常利益÷売上高×100
これらの数値を用いて収益性分析(資本利益率分析)を行います。他にも、利益増減分析や損益分岐点分析などで収益性を分析できます。
安全性
安全性とは、負債と資本の比率から、企業として支払い能力があるか、また財務が安定しているかを表すものです。企業間の取引や、銀行が融資を判断する際の材料となります。安全性が高ければ、借入金の返済能力が高いということです。一方、安全性が低ければ、資金繰りが困難で倒産のリスクが高まると考えられます。
安全性分析に用いられるのは以下のような数値です。
- 流動比率=流動資産÷流動負債×100
- 当座比率=当座資産÷流動負債×100
- 固定比率=固定資産÷自己資本×100
- 自己資本比率=自己資本÷総資本×100
生産性
生産性とは、企業の資本をどれだけ製品・サービスの販売や売上アップにつなげられているかを表すものです。資本とは、ヒト・モノ・カネ・情報を指し、それらがどれほど付加価値を生み出しているかによって生産性の高低が判断できます。生産性分析には、以下のような指標が用いられます。
- 労働生産性=付加価値÷従業員数
- 資本生産性=付加価値額÷有形固定資産
- 労働分配率=人件費÷付加価値額×100
成長性
成長性とは、企業の売上高や利益がどの程度伸びているのか、また今後どれだけ成長が見込めるのかを表すものです。成長性がプラスであれば、企業の売上や顧客数などが増加していることを示し、マイナスであれば縮小していることを示します。
自社の数値を算出したあと、市場と比較することで、自社の勢いや存在感を把握できます。具体的には、以下の指標で成長性分析を行います。
- 売上高増加率=(当期売上高−前期売上高)÷前期売上高×100
- 経常利益増加率=(当期経常利益−前期経常利益)÷前期経常利益×100
- 総資本増加率=(当期総資本−前期総資本)÷前期総資本×100
- 純資産増加率=(当期純資産−前期純資産)÷前期純資産×100
- 従業員増加率=(当期従業員数−前期従業員数)÷前期従業員数×100
活動性
活動性とは、どれだけ資本を有効活用して売上増加できているかを表すものです。活動性が高ければ、少ない資本で売上を上げられていることになり、低ければ資本を投入しても十分な売上が得られていない状態を表します。
以下の指標で活動性分析を行うことが一般的です。
- ・総資本回転率=売上高÷総資本
- ・固定資産回転率=売上高÷固定資産
- ・棚卸資産回転率=売上高÷棚卸資産
経営分析について、詳しくは以下の記事を参照してください。
基本の経営指標を理解し、タイムリーな経営判断を行うには
VUCA(ヴーカ)の時代とも言われる今、実践すべきなのはタイムリーな経営判断です。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧さ)の頭文字を取った言葉です。これは、予測が困難で変化が激しい現代の経営環境を指します。
このような環境では、迅速で柔軟な経営判断が求められるため、細かな数字の変化にも敏感になっていかなければなりません。しかし、一般的な経営指標は決算書の数値をもとに算出するため、数字の更新は、上場企業であれば半期に1回、非上場企業では年に1回となります。決算書の分析だけでは、タイムリーな判断は難しいのが現状です。そこで、必要なタイミングに最新の数値を用いて経営判断を行うために必要なことを3つ紹介します。
経営の見える化を行う
企業の意思決定を行う際は、まず現状を数値で見える化することが重要です。本ブログを運営する株式会社オロが2022年に行った『知的サービス業<数字で語るマネジメント>に関する実態調査』(*1)によると、数字をもとに意思決定を行う会社ほど売上目標の到達率が高いことがわかりました。
また、日々数字によるコミュニケーションを実践している会社は、売上目標の到達率が高いことも判明しています。つまり、経営が数字で見えるようになれば、売上向上につながる可能性が高いということです。
正確な数値を集約する
数値で見える化するためにも、正確な数値を社内で集約することが肝要です。数値が不正確、もしくは曖昧であれば、現状を正確に把握できず、判断ミスにつながる恐れがあります。
ミスを防ぐための方法として、システムやツールを活用して正確な数値を集約できる体制の整備が考えられます。また、規定のフォーマットを準備し、誰もが同じ基準のデータを集約できるように仕組みを構築することも大切です。
モニタリングしやすい環境を整える
集約したり指標として用いたりしたデータは、セグメント別(月別、クライアント別、案件別など)や昨年との比較をすぐにモニタリングできることも重要です。単体の数字だけではわからないことも、クロスセル分析を行ったり図表化したりすることで、数値の傾向や変化が視覚的に把握でき、経営の方向性や対策すべき箇所がわかりやすくなります。現状のデータをモニタリングしやすいツールの導入も有効です。
経営判断の質を高めるにはシステムとBIツールの活用がおすすめ
経営分析の手法として、財務諸表(財務三表)を活用した基本的な経営指標を活用する以外にも、さまざまな分析手法が存在します。膨大なデータから適切な経営判断を行うためには、指標の特性を理解し、それぞれの用途に応じて指標を算出し、見える化、モニタリング体制を整えることが重要です。
その際、過去のデータ分析だけでなく、今後の見通しを立てることも大切です。よりタイムリーなデータ分析を行うことで、質の高い経営判断を実現できます。そこで有用なのが、システムとBIツールの活用です。システムを使用してリアルタイムで正確なデータを収集したうえ、BIツールを活用することで大量のデータをもとにした適切な分析・見える化ができます。
特に社内の経営資源のデータを一元管理するERPとBIツールを連携することで、経営に関わる多くの情報をスムーズに取り込んで分析できるようになります。現在使用しているERPがあるなら、それと連携可能なBIツールを選ぶといいでしょう。
これからシステムを新たに導入する場合は、ERPとBIツールが連携できるシステムを導入すると、手間やリスクを抑えられるのでおすすめです。